マンガやドラマで人気のテセウスの船。TVドラマは3月22日でいよいよ最終回を迎えます。真犯人は果たして誰なのか!?気になるところですが、ストーリーの結末はTV放送にお任せし、今回はこの「テセウスの船」という言葉について解説します。
今回の内容はコチラ(目次です)
「テセウスの船」とは、古代ギリシャ生まれの哲学の言葉
ところで、テセウスの船とは一体何でしょうか。「テセウスって人の名前だよね?あんまり聞かない響きだけど誰だろう?」と思った方。ピンポーン!いい線いってます。
それもそのはず、テセウスとはギリシャ神話に出てくる王子様の名前。半分が牛の怪物ミノタウロスを倒したとされる英雄です。
その英雄テセウスの乗っていた船が「テセウスの船」なのですが、この船がどうして現代の日本にまで伝えられているのでしょうか。まして、人気のドラマのタイトルにもなるなんて、何か秘密がありそうです。
それもそのはず、この「テセウスの船」は古代ギリシャの哲学者たちの間で、大問題となってしまったのです。そして、その問題は今も解決されていません。一体どんな難問なのでしょうか。
ここからは、このテセウスの船がどんな問題だったのか見てみましょう。
簡単そうで解けない!?哲学者たちを悩ませたパラドックス
怪物ミノタウロスを倒し、意気揚々と帰ってきた英雄テセウスは人々に歓喜の中で迎えられました。そして、テセウスの乗っていた船は大切に保存されることになります。
ところが、荒波を乗り越えた木造の船はあちこち傷だらけ。やむを得ず船底の板や帆などを取り替えました。部品交換です。ところが、ここである老人がおかしなことを言いました…
「おいおい、板を変えちまったら、元の船じゃなくなってしまうぞ!」
ん?
人々は「何を言っているんだ?」という反応で、老人の言葉に耳を貸しません。
それもそうでしょう。傷んだ部品を交換するのは当たり前のことで、それで元々の物と変わってしまうなんてことは考えられないでしょう。
月日は過ぎ、テセウスの船についても、最初に取り替えたところ以外についても傷みが出てきてしまい、そのたびに部品交換を繰り返します。おかげで船はきれいなまま保存されていました。
そうしているうちに、また、別の男がこんなことを言いだしました。
「あれ、この船ってテセウス様が乗っていた時の板って1枚も残ってなくね?」
誰もが絶句しました。
確かに、最初のうちは傷んでいた一部を交換しただけ。例えば100枚ある舟板のうち3枚を交換したとしても、誰も気にも留めないでしょう。
ところが、修理が進むにつれ、100枚の舟板のうちの30枚、50枚、80枚とどんどん交換する部分が増え、ついには全ての部分が交換され、もともとのモノが1枚も残っていないとしたら…その船は元の船と呼べるのか?
これには、誰からも「こうだ!」という答えが語られることはありませんでした…
テセウスの船の問題についての哲学者たちはどう考えたか?
この問題について、考え方としてはいろいろとあるでしょう。主要な2つの考え方についてみてみます。
考え方1 ~部分を変えると全体が変わる~
まずは、「部分を変えると全体が変わる」という考え方についてみていきます。テセウスの船の話に即して言えば、「舟板を変えてしまったのだから、厳密にはもう元の船と一緒だとは言えないよね」という考え方です。
この考え方だと、「どの時点で変わったのか」という新たな疑問が出てくることになります。そして、これもかなり難問です。
100枚のうち、80枚交換した時点だと「かなり違う」、50枚交換した時点だと「まぁまぁ違う」、では3枚だとどうでしょう。「ちょっとだけ違う?」という言い方ができるかもしれません。ですが、どれも主観的な見方によるものであり、誰もが納得する答えとは程遠いと言わざるを得ません。
ちょっと身近な例を挙げると、学生時代にお互い貧乏学生だった友人が、数年後再開しご飯を食べに行った時など、一人は以前のまま、店で一番安い「Aランチプレート」を注文したのに、もう一人は全く迷わずに「さいころステーキセット、デザート付きで!」などと頼もうものなら、Aランチの彼は
「おい!お前いつの間にそんなエラそうなものを食べるようになったんだ!変わっちまったな!」
なんて思うかもしれません。でも、さいころステーキ君は、まさか自分が変わったとは思っていないことでしょう。(どこが身近だ)
この考え方は、主観的には納得しやすいかもしれませんが、皆が納得できる客観的な基準とはなり得ないと言えます。
考え方2 ~部分を変えても全体は変わらない~
次に、部分を変えても全体は変わらないという考え方についてみていきます。
この考え方だと、変化の量が少ないうちは納得しやすいでしょう。ただ、全ての部分が入れ替わっても「元のものと一緒だ!」と言い切るのはかなりムリがありそうです。
ですが、実際には私たちは実は多くこの考え方を受け入れていることもあります。
例えば、私たちの身体について考えればどうでしょうか。
私たちの血液や細胞は日々新陳代謝によって入れ替わっています。骨や心臓も数か月で細胞が入れ替わると言われています。脳など一部の細胞を除き、私たちの体の細胞は、生まれた時のものは既に不用品として体外に捨てられており、同じものはほとんど残っていないのです。
それでは、私たちは生まれたばかりの赤ちゃんの時とはことなる人間になってしまったのでしょうか。細胞など一部に注目すれば、「もう、私は赤ちゃんのときの私ではないのよ!」と言うかもしれませんが、普通の日常生活を送っている間は、自分が入れ替わっているという実感はほとんどないのではないでしょうか。
あるいは、こんな例はどうでしょう。
江戸時代にある人が和菓子の店を創業したとします。創業者や番頭の働きにより、この和菓子屋は順調に成長していきました。年を重ねた創業者は、後進に事業を託し、自らは隠居を楽しみながら、幸せな生涯を終えました。
この和菓子屋はその後も成長し続け、江戸時代から明治に移るころには洋菓子にも事業を広げました。その後戦争もありましたが、辛くもやり過ごし、昭和、平成と時代を乗り越え、事業もお菓子だけでなく、サプリメントや健康食品に手を伸ばし、急速に拡大していきました。
ついに21世紀になり、令和に入るころには、ネットビジネスを展開し、主な事業はITソリューションやアプリ開発がメインとなり、本社の場所も、創業当時の江戸城の近くから、アメリカのシリコンバレーに移しており、外資も取り入れ、経営人の日本人比率はほぼ10日%となっていました。
少し極端な話ですが、もし、創業者が天国からこの会社の様子を見たときに、果たして「自分の創業した和菓子の店」と同じだと思うでしょうか。
思うかもしれないし、思わないかもしれない。また、どのあたりで「変わった」と感じるかはかなり違うと思います。
パラドックスとは?
このように、どのように考えても解決が見つからない問題を哲学の世界では「パラドックス」あるいは日本語で「逆説」と呼びます。パラドックスは古代ギリシャ以降、様々な難問が考え出され、多くの哲学者たちが解決を挑みましたが、満足のいく答えは見つかっていません。
「テセウスの船」はこのようなパラドックスの一つなのです。
ところで、ここまで読んで、パラドックスなんてなんの役に立つのかと思っている人もいるのではないでしょうか。
「解決できる問題なら考えてみたいけど、どうせ答えなんか出ないんだろ!意味ないじゃん」
確かに、パラドックスはどう考えても解決できない問題です。逆に、解決できてしまうならパラドックスではありません。解決できないからパラドックスなのです。
パラドックスを考えることのメリット 3つ
そして、このような問題を考えることには、実は大きな意味があります。それは、
1、物事の本質を見る練習になる
2、思考の持久力がつく
3、広い視野を持つことができる。
ということが言えます。
それ以外にも、こうした問題を考えることは知的パズルを解くという感覚で、純粋に楽しいということもあります。正直、私自身は、この楽しさこそ第一です。まぁ、これについては人それぞれだと言えるでしょう。
まとめ
現在放送中のドラマ「テセウスの船」というタイトルには、実は古代ギリシャから哲学者を悩ませてきた深い難問が潜んでいる、という話をしてきました。
ドラマをみていると、この難問を思い起こさせる場面がチラホラと出てきます。この言葉を知っているかどうかで、ドラマの楽しさを深く味わうこともできます。
また、「テセウスの船」のようなパラドックスに触れることは、思考の力を鍛えるのにはうってつけです。
「テセウスの船」問題とぜひ楽しく格闘してみてください。
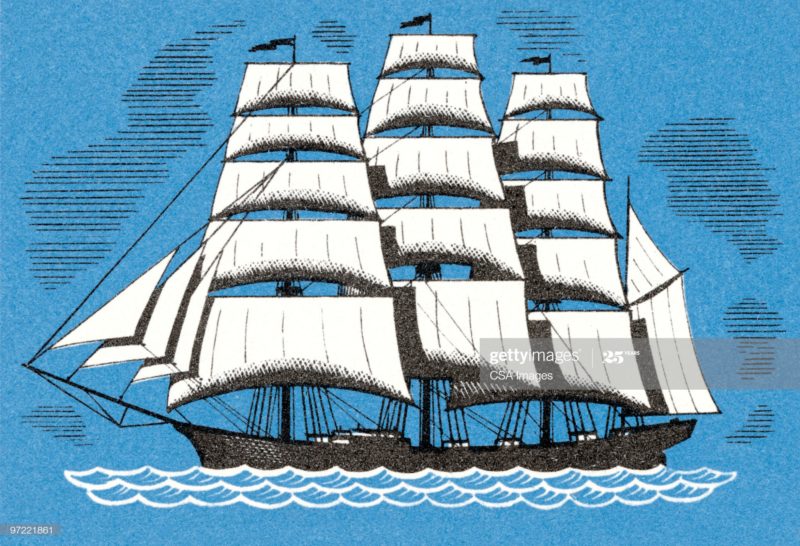




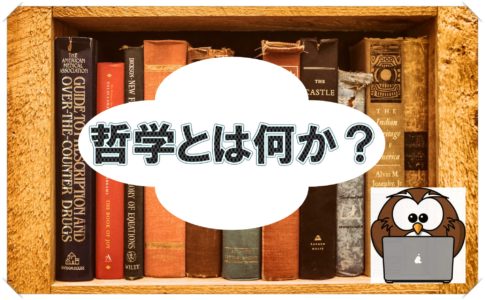


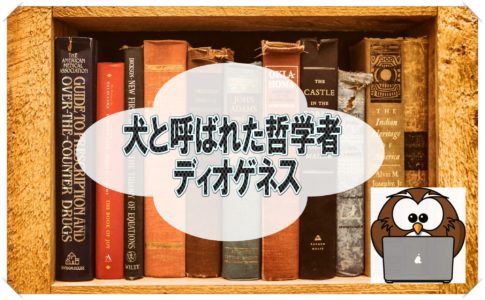




コメントを残す